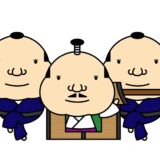この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
これは、高田藩主(越後高田)榊原政敬に従い上洛したある高田藩士が書いた幕末の日記です。
日記は、文久3年(1863年)12月に京に行くことになったところからはじまり、元治元年7月に高田(現上越市)に帰って来るまでのことが書かれています。
江戸時代に現在の東京日本橋(江戸)~京までを結ぶ道を東海道53次といいました。この日本橋というのは、奥州街道・日光街道・中山道・甲州街道・東海道の五街道の起点です。ちなみに橋名板の日本橋の文字は徳川慶喜によるものです。
「お江戸日本橋七つ立ち、初のぼり、行列そろえてあれわいさのさ、こちゃ高輪夜明けて提灯消す、こちゃえ・・・・」とコチャエ節に唄われたように早朝4時に日本橋を出発して高輪に来てようやく夜が明け、提灯を消して旅に出るというのが一般的だったようです。
現在では、新幹線、飛行機などの交通機関を利用して日帰りで行き来できますが、当時の交通手段は、徒歩、馬、駕籠などでした。
1日30km~40kmの距離を歩いていたといわれ、江戸から京都までは約500kmあるため約2週間の日数が必要でした。
しかも橋がないところも多く、川留めなどで日程が大幅に遅れるといったこともありました。その東海道を高田藩士が急ぎ旅をしている場面なのですが、箱根の関所でなにか問題があったようです・・・。
同(12月)15日 雪が少々降った。江戸表を出立して夜に神奈川 新岡屋方に泊まった。里数は七里(28km)だった。
雪が降る中、江戸を出発して夜に神奈川宿 新岡屋に到着・宿泊したようです。
歌川広重が描いた「東海道53次 神奈川宿」には急坂の高台にたくさんの茶屋が描かれて、その左側には綺麗な海が描かれています。ここは台の茶屋とよばれ、海を一望することができて人気だったようです。
また、絵には「さくらや」と描かれた茶屋がありますが、その後売りに出され、旅籠「田中屋」となりました。創業は1863年(文久3)らしく、この高田藩士たちが旅をしているころに創業し、現在でも老舗料亭として営業中です。
ちなみに坂本龍馬が亡くなったあと、妻のおりょうが中居として働いていたこともあったようです。
同(12月)16日 天気 大磯宿 鈴木屋方へ宿泊 里数九里半九丁(約39km)

1里が約4kmで、半だから約2kmと1丁が109mだから・・・981mほど

ぜんぶで約39kmだね~
同(12月)17日 曇天 小田原宿 柳屋由蔵方に宿泊 里数四里也(16km)

大磯宿から小田原宿は16km
小田原宿は神奈川県内で最大規模の賑やかな宿場町でした。
小田原宿を超えるためには酒匂川を越えなければならないのですが、防衛上の理由から、渡し船の運航を禁じていて、10月~2月の間だけ仮橋が架けられますが、それ以外は川越人足に頼っていました。値段は川の深さ、川の渡り方(肩車 輦台)などにより値段が変わりました。
小田原宿は、薬屋さんがめまいや気つけに効く「透頂香」の口直しとしてお客さんに出した「ういろう」が人気となり名物となっています。
また、小田原提灯や、木の板にのせて扇型の形にしたかまぼこも小田原が発祥といわれています。

箱根関所は、ここを出入りする人や物を監視するために設置された重要な施設で、特に入鉄砲に出女(江戸に入る鉄砲と江戸から出ようとする大名の妻)が厳重に取り締まられました。
旅人が通る際には身元チェック、不審な点はないかなどの様々な厳しい検査を受けます。そして、許可を得ないと通過することができませんでした。
また、手形などに不備があった場合は発行元に戻り再発行してもらわなければなりませんでした。
箱根関所の住所 神奈川県足柄下郡箱根町箱根1番地
一、箱根関所証文印鑑に不備があったため、同宿より神岡市右衛門、高橋定治の2人が早駕籠で江戸上屋敷まで戻った。

あら、大変 江戸まで戻るの?!

小田原宿から箱根の関所まで17kmで、小田原宿まで引き返したんだから17km、、

それだけでも大変~
江戸表~神奈川 新岡屋 28km
神奈川 新岡屋~大磯宿 鈴木屋 39km
大磯宿 鈴木屋~小田原 柳屋 16km

小田原から江戸まで83kmだ・・

早駕籠の時速は6kmくらいなんだって

83kmを早駕籠が時速6kmの場合は、・・

83kmは片道だから、往復すると・・

往復すると166km、約28時間くらいかかるね~
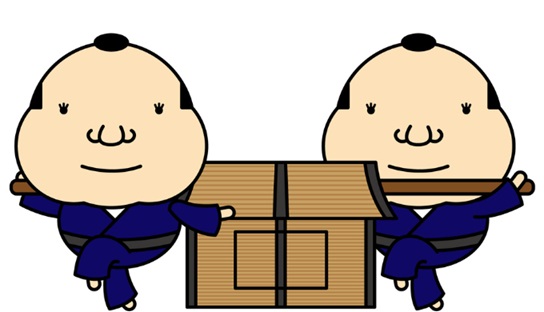
右 ↑ につき翌日の18日も同宿に逗留した。
同(12月)19日 曇天 昼九ツ過ぎ(お昼の12時ころ)両人(神岡市右衛門、高橋定治)が帰ってきたのですぐさま出立した。雪が降っていた。
箱根の関所証文印鑑に不備があり、神岡市右衛門と高橋定治の二人は早駕籠で江戸の上屋敷まで戻ります。 小田原宿から江戸の上屋敷までの距離は83km、往復で166kmを早駕籠で走り続けたと思われるので大変だったと思います。
一方残った高田藩士たちは18日も同宿に逗留とあるので、小田原宿 柳屋由蔵方に宿泊しました。

到着してすぐに出立って大変だったね

腰が痛かっただろうね~
箱根宿 大村屋傳兵衛方へ宿泊した。里数四里八丁(約16.9km)
高田藩士たちはやっと証文が整い箱根の関所を通ることができたようです。しかし、難所といわれる峠を2回も越えたとは藩士たちの大変な旅の様子が伝わってきます。

無事に箱根を通過できたんだね~
箱根八里八丁の峠なり

箱根八里?里数は四里だけど・・

小田原から難所である箱根、そして三島宿までの道のりを箱根八里と呼んでいたみたい

でもまだ三島宿に着いていないよね~・・?? 2回通ったから?
その夜、弐尺ほどの雪が降り積もった。翌朝 出立のときには大吹雪でとても難渋した。

弐尺~?

1尺が30.3cm 弐尺は60.6cm

結構積もったんじゃない?!

雪国育ちでも大吹雪で大変だったみたいだね~
同(12月)20日 雪 吉原宿 山田屋彦五郎方に宿泊 里数十里六丁(約40.7km)
ここの宿場町は当初はもっと海に近かったそうなのですが、高潮被害で内陸に2回移転をしているそうです。
このために街道を北に大きく迂回したことで、江戸から京へ行くときに右側に見えていた富士山が左に見えることから「左富士」と呼ばれ吉原宿名物となりました。
同(12月)21日天気 府中 河内屋惣兵衛方に宿泊 里数十里也(40km)
徳川家康のお膝元で最大規模の宿場町として賑わいがありました。府中宿の安倍川には橋がないために川越人足の徒歩渡しで対岸に連れて行ってもらいました。
ちなみに、安倍川餅は家康が名付け親とされています。というのも家康が茶屋に立ち寄ったときに、きな粉を安倍川で取れる金に見立て「安倍川の金な粉餅」という名前で献上したところ、家康が気に入って「安倍川餅」の名前を与えたといわれており、それが名物となりました。
同(12月)22日 同断(天気)日坂宿 川坂屋治右衛門方に宿泊 里数十里十一丁(約41.2km)
同(12月)23日 同断(天気)浜松宿 鶴屋清兵衛方に宿泊 里数九里半廿六丁(約40.8km)
浜松宿といえば浜松城で、出世城として知られています。家康が駿府城に移ったあとに浜松城の城主になった殿様は次々に幕府の要職についたことから「出世城」と呼ばれるようになったそうです。
同(12月)24日 同断(天気)赤坂宿 若狭屋清右衛門方に宿泊 里数十里半廿五丁(約44.7km)
御油宿からわずか2kmしか離れていないところにある宿場で、東海道53次の中で最も間隔の狭い区間です。
もともとは赤坂御位宿といった一つの宿場町だったそうなのですが 大きすぎて家康によって2つの宿場に分けられたそうです。
西(京の方)から来た大名は赤坂宿、東(江戸)から来た大名は御油宿を利用するといったルールもあったようです。
法蔵寺 徳川家の祖である松平家ゆかりの寺で、参勤交代などで通る大名は参詣していたといわれています。家康が幼少期に読み書きを習った寺で手習いのときに水を汲んだ御霊泉もあります。
同(12月)25日 風 宮宿 竹中屋源兵衛方に宿泊 里数十二里七丁(約48.8km)
同(12月)26日 雪降り 同宿逗留 節分だった。

12月で節分?

旧暦の立春らしいよ~
右 ↑ の訳は桑名七里舟渡しが雪荒れのために出なかったので逗留となった。
12月25日の赤坂宿~宮宿は風が強かったとあり、12月26日は七里の渡し船が雪のために欠航となったようで、宮宿に25日と26日と2日連続で宿泊しています。
宮宿は佐屋街道、美濃街道への分岐点が有り、熱田神宮の門前町であったために非常に栄えた宿場町でした。次の宿場の桑名へは「七里の渡し」と呼ばれる船で東海道唯一の海路を移動していました。
船は午後4時までで、乗り遅れた旅人や欠航などで船が出ないときはこの宿場に泊まりました。そのため旅籠の数は248軒もあり東海道で最多といわれています。
七里の渡し
宮宿(愛知県名古屋市)と桑名宿(三重県桑名市)までの海路で、距離が7里(約28km)であったことからこう呼ばれています


七里の舟渡しって雪のために船が出なかったんだね~

雪荒れってあるから天候がものすごく悪かったんだね
同(12月)27日 天気 四日市宿 白木屋長左衛門方に宿泊 十里八丁(約40.9km)
室町時代に定期市が開かれるようになり(毎月4の付く日に市が開かれた)ことから四日市と名付けられたといわれています。
名物はなが餅です。(小豆餡が入った平らで長い餅) 伊勢神宮へ行く二の鳥居がある東海道と伊勢街道の分岐点がありました。(日永の追分)

次は土山宿からだよ~

つづく