この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
葛飾北斎(かつしかほくさい)とは世界に名を馳せる浮世絵師として知られており、作品は日本の文化を象徴する存在で、「富嶽三十六景」は日本のパスポートのデザインにもなっています。
しかし、やはり根っからの芸術家のせいか少々変わり者だったようで・・今回はそんな北斎の生涯と驚きのエピソードをゆる~く紹介します。
葛飾北斎は東京都墨田区で生まれ、幼少期から絵を描いており、14歳のころには浮世絵版画の修行をはじめ、その後 役者絵を描く勝川春章に入門し、勝川春朗という名前で挿絵などを描いて活動していました。
1792年に勝川春章が亡くなると兄弟子であった勝川春好に破門に近い形で勝川一門から追い出されてしまいます。のちに大人気絵師となった北斎は、このことがなかったらここまでこられなかったと語ったといわれています。
1798年 破門されたあと俵屋に入り「俵屋宗理」(たわらやそうり)を名乗っていましたが、その後 独立して「北斎辰政」(ほくさい ときまさ)と名乗り、絵師 北斎としての道を進むことになります。
江戸時代の出版王と呼ばれた蔦屋重三郎と出会い、戯作者である曲亭馬琴を紹介されたことで、馬琴の物語の挿絵を数多く描くことになります。
この二人は一時共同で生活するほど親しかったようですが、お互い芸術家同士なので作品に対してのこだわりが強く口論が次第にエスカレートしていき、喧嘩別れしたともいわれています。それまではたびたび版元がとりなしていたらしいのですが、とうとう双方が仲直り不可というところまできて絶縁に至ったといわれています。

ちなみに北斎の挿絵と馬琴の読本で有名なのが「椿説弓張月」「そののゆき」があります。
*曲亭馬琴(戯作者) 南総里見八犬伝を執筆した人で、48歳で書き始め28年にわたって書いたとされ、65歳くらいから視力を失いかけ、やがて視力が完全に失われると息子の妻、お路(みち)の口述筆記で完成させたといわれています。
北斎が70歳を過ぎたころ名所を描いた「富嶽三十六景」が大ヒットとなります。
このデザインは有名なのでどこかで見たことがあると思います。新千円札をお持ちの方は裏面をご覧ください。それが北斎の浮世絵です。

*富嶽三十六景・神奈川沖波裏
海外でも北斎スケッチとよばれる北斎の代表作「北斎漫画」を描きます。
北斎漫画とは絵の手本を描いたもので数多く出版されました。それまでは門人に肉筆で絵手本を渡していましたが、門人が増えすぎたことと、多くのファンや絵を学びたい人達のために版下絵の制作に取り掛かります。
それにより大量に摺って出版することができました。
その後亡くなる少し前まで肉筆画を描き続けるようになります。
みずから「画狂老人」といって多くの作品を描いた北斎は90歳でその生涯を閉じました。
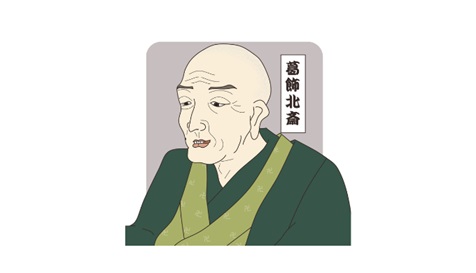
晩年の北斎と一緒に暮らしていたのは後妻こと(ことは北斎が69歳のころ亡くなります) との間に生まれた三女 阿栄(おえい)でした。阿栄は、顎が出ていたといわれ、北斎はこの娘を「アゴ」と読んでいたらしいです。
また、葛飾応為として多くの美人画を描き、北斎は美人画は阿栄の方が優れているというほどだったようです。
そんな阿栄ですが、絵師の南沢等明と結婚していましたが、等明の描いた作品を指して笑ったことが離縁に繋がったといわれており、それを機に実家に戻ったようです。
しかし北斎が亡くなって数年後に家を出たきりどこへ行ったか分からないといわれています。
天才と呼ばれた人は多くの面白いエピソードを残してくれますが、北斎もやはりその一人でした。有名なものをご紹介します。
ある日オランダ商館のカピタン(商館長)から2巻で1組の絵巻物の注文を受けましたが、そこに同行していた医師からも同じものの注文を受けます。
北斎は注文通り品物を届けますが、医師は薄給を理由に値切ってきたのでした。それを断ると、1巻だけ買うと言い出したので、北斎は怒って絵を持ち帰りました。
理由として、そのまま絵を売ればそのときはいいけれど、のちに異国に屈して値切って売ったとなれば日本の絵師として絵の価値が落ちてしまうといったものでした。
この話を聞いたオランダの商館長は北斎の絵師としてのプライドに感心して、医師が注文した絵巻物も買い取ったといいます。
1827年 北斎は68歳(生まれた年を1歳としています)のとき脳卒中で倒れ、一時は後遺症で筆が握れなくなります。
しかし北斎のすごいところは、柚子と酒をつかった薬を自ら作りそれを飲んで奇跡的に復活したというところです。
そして倒れた翌年には作品を出版するほどに回復してみせたのですから驚きです。

生涯で93回も引っ越したようで、「引越し魔」と呼ばれるだけはあります。酒も煙草も食事さえ興味がなく、ただひたすら絵を描き続けました。
そして、お金にも執着がなく、支払いは中身をみないでお金が入った袋をそのまま渡していたそうです。
そんな北斎だから家の中の掃除などするわけもなく、ゴミで部屋が汚くなると引越ししたといわれています。
また、北斎の孫がつくる借金のためにお金がなくなり、着ている衣服はボロボロで、版元にお金を借りるといった生活をしていたようです。
先妻の長女阿美与(おみよ)と絵師 柳川重信の子であり北斎からみれば孫ですが、借金ばかりして、北斎からは「悪魔」と称されるほどの悪行を重ねたらしく、この孫のことでずいぶんと悩まされたといわれています。
そして孫が起こした事件のために名前まで変えて潜伏生活を送っていたともいわれています。
この潜伏生活には様々な説があって、作品が幕府の意に沿わないもの(禁止されていた作品)を出してしまい逃げていたという説や、借金取りから逃げていたとの説もあります。
しかしこの孫を追い払うため、晩年には毎日獅子を描いて魔除けにしたとの話もあり(長寿を願った説もあり)、相当放蕩の孫であったということが伺えます。
絵を描く以外には興味を持たなかった北斎ですが、90歳で亡くなるときに「せめてあと5年生かしてくれたら、本当の絵描きになってみせる」といったというのですから北斎の創作意欲が最期まで凄まじいものだったことが分かるエピソードだと思います。

・・・・・
江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎は絵だけではなく、ファッションやデザインの世界でも影響は見られ、日本のパスポートや新紙幣などで一層身近なものになって現代でも多くの人に親しまれています。

以上 ゆる~い葛飾北斎さんの紹介でした

